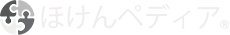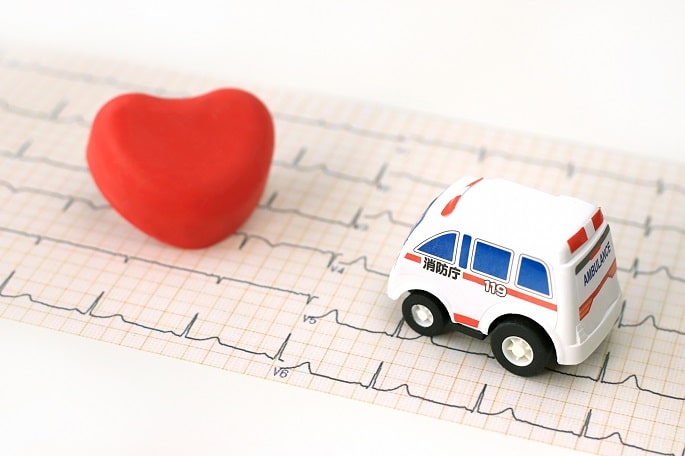最近は、医療保険しか加入していないという方も多くいる一方で、医療保険は本当に必要なのかと考える方も増えてきているのではないでしょうか。いる、いらないを決める前に、医療保険というそのものについて考えてみましょう。
そもそも「医療保険」ってどんなもの?
死亡保険に入院保険特約として販売されていたものが、2001年に第三分野保険が自由化され国内生命保険会社、損害保険会社が本格参入をして「医療保険」そのものが多く販売され始めました。
主には、
入院日数に応じた給付金。
手術内容に応じた給付金。
先進医療を受けた場合の技術料実額の給付金。
これらに加えて、通院給付金、三大疾病入院給付金や入院一時金、女性疾病入院給付金等、「特約」と呼ばれるさまざまオプションが数多く存在しています。
どんなものか?と聞かれると、病院や診療所でその治療を目的に入院や手術をした場合に、民間保険会社より給付金を受取るための保険ということではないでしょうか。
医療保険不要論の主な理由
不要論で多く聞かれる理由としては下記について。
公的医療保険制度の充実
日本では国民皆保険制度が確立されており、世界最高レベルの平均寿命と保健医療水準が維持されています。
基本的にはどこの医療機関でも、どの医師にも自由に診てもらえて治療が受けられます。
病院の窓口で払う医療費の自己負担は、年齢や所得によって異なりますが、原則として3割の負担となっています。
また、70歳以上の場合は所得に応じて1割~3割に分類され、6歳未満の未就学児は2割の負担です。
18歳までかかる医療費が無償という医療費助成を行っている自治体もあります。
このように、日本では少ない自己負担で誰もが安全で質の高い医療サービスを受けることができる環境があるため、民間の医療保険はいらないと考える方もいるようです。
「高額療養費制度」の存在
公的医療保険、いわゆる社会保険についても知っておかなければいけません。
同一月(1日~月末)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度です。医療費が高くなることが事前に分かっている場合は「限度額適用認定証」を提示すれば、一時的立替も不要です。
一定の金額は年齢、所得により異なりますが、例えば70歳未満で標準報酬月額28万円~50万円の方の場合は
80,100円+(総医療費-26,700円)×1% を超えた金額が払い戻されます。
4か月目以降は、44,400円となります。
但し、差額ベッド代や食事代等の保険適用される診察費用以外の費用は対象とはならず全額自己負担になります。
一部負担還元金・家族療養費付加金
加入している健康保険組合によっては、「一部負担金還元金・家族療養費付加金」や「一部負担金払戻金・家族療養費付加金」などの高額療養費制度とは別に健康保険組合が独自で実施している場合があります。
例えば、自己負担額25,000円を超える金額が給付されるという組合もあります。その場合、どんなに高額な医療費がかかったとしても、自己負担額は25,000円ということです。
ご自身が加入している健康保険組合に確認してみましょう。
貯蓄での対応が可能
生涯を通じて、保険で保障された給付金等よりも保険に支払った保険料の金額の方が高くなるケースがあります。
起こるか起こらないか分からない入院や手術の費用に対し、民間の医療保険の加入で備えるよりも、お金を貯めることで、負担する医療費に備えるという考え方もあります。
病気やケガで入院したという場合に、金銭面のカバーをしてくれるのが医療保険です。
日本の公的保障は充実しており、自己負担額の支払いには全く問題がないぐらいの十分な貯蓄がある場合、医療費の自己負担部分は貯蓄から賄うことができるため、民間の医療保険に加入する必要性はないと考える方もいるようです。
保険料が家計の負担になる
民間の保険会社が販売する医療保険には様々な種類があり、また、様々な症状に対応した特約を付加することで、多くの症状をカバーすることが可能です。
しかし、全ての病気やケガの治療に対応する医療保険に加入しようと思うと、保険料の負担が大きくなります。
例えば、入院給付金日額が10,000円(1日あたり)の医療保険に、先進医療特約、女性疾病特約、三大疾病特約等の特約を付加し、様々な病気やケガの治療に対応できる医療保険に加入したとします。
このようにいろいろな特約を付加すると保険料は高額になりやすく、医療費へのカバーには高いとお感じになられる方も多いと思います。
特に高齢で加入した場合、さらに保険料が高くなりる傾向があります。
安心を得ようと加入した医療保険の保険料が高額になり、家計への負担になる場合があります。
結果的に民間の医療保険は必要ないと考えることもあるでしょう。
医療保険は本当に必要?不要?と悩むその前に
そもそも、何が必要なのか?ということを考えなければいけません。
病気やケガで入院した時に「医療保険」という商品が必要なのではありません。窓口に払う医療費や、それ以外にかかる費用が必要なのです。
小さなお子さんがいる場合、入院期間中のベビーシッター代が必要であったり、近隣に専門医がいない場合は、県外に行く交通費が必要であったりと人それぞれ入院に伴う必要な費用は異なります。
いずれにせよ、その時にその費用をどこから調達するかは事前に考えて備えておかなければなりません。
「高額療養費制度」見直しの可能性は?
70歳以上が対象でしたが、平成29年、30年と、自己負担の増額が行われました。(高額療養費制度を利用される皆さまへ 厚生労働省参照)
今後も高齢化社会、人口減少に伴い高額療養費制度をはじめ、社会保険制度の見直しはされるものと予想されます。
高額療養費制度があるから備えは不要とは、これから将来は言えないかもしれません。
時代のニーズに合った商品
各保険会社が、今後もいろいろな保険商品を開発、販売していくと思われますが、入院の短期化、在宅医療、自己負担の増額等、環境の変化にどこまで対応できるかも考慮しなければいけません。
いずれにしても、医療保険一つだけで備えは十分という商品を探すのは難しいかもしれません。
自分には必要?不要?判断基準はどこ?
判断基準は、入院した時に何の費用がいくら必要で、その費用を賄えるかどうかです。
あとはその資金調達をどこからするかだけなので、医療保険はその選択肢の中の一つであると考えれば良いかと思います。
医療保険が必要と考えられる人の特徴
医療保険の必要性は個人の状況によって異なります。
前述のとおり、そもそも、公的医療保険制度が充実しているので医療保険は必要ないと思われている方もいらっしゃいます。
また、医療保険の加入により、保険料が家計を圧迫することもあります。
高額な医療費に対応できる貯蓄があり、経済的に余裕がある方は医療保険の必要性は低いと思われるかもしれません。
一方で、公的医療保険制度でカバーできない費用に備えたいと思われる人や、年齢を重ねることで今の健康状態がそのまま続くと思えず、将来に備えたいと考える人は、医療保険の必要性を感じていらっしゃるかもしれません。
一方で、病気やケガの医療費対策よりもそれによる収入の減少に備えたいという人もおられるでしょう。
自営業やフリーランスの人
自営業やフリーランスの人が加入する国民健康保険は会社員が加入する健康保険と比較すると、保障が限定的になります。
国民健康保険には傷病手当金の制度がなく、病気やケガで働けなくなった際の収入の減少をカバーする手段が限られています。出産手当金の制度もありません。
また、健康保険の保険料は会社と従業員が折半して払うのに対し、国民健康保険は全額が加入者の自己負担になります。
個人事業主やフリーランスの人が病気やケガで働けなくなった際は、収入が途絶え、生活が厳しくなる場合もあります。
自営業やフリーランスの人は、積極的に医療保険の加入を考えても良いでしょう。
貯蓄が少ない人
生命保険文化センターの「生活保障に関する調査」では、1日の入院にかかる自己負担費用は平均で20,700円、直近の入院時の自己負担費用の総額の平均は19.8万円となっています。
ケースによっては100万円を超えることもあり、支出が貯蓄を超えてしまう危険性があります。
高額療養費制度があるとはいえ、自己負担額や保険適用外の費用は発生します。
更に収入が減少し、日常生活に支障をきたすような人もいらっしゃるでしょう。
貯蓄が十分でない場合、突然の医療費負担が家計に大きな影響を及ぼす可能性があります。
貯蓄が少ない人は、医療保険の加入を検討されても良いかもしれません。
参照:生命保険文化センター「2022(令和4)年度生活保障に関する調査」 第Ⅱ章 医療保障
https://www.jili.or.jp/files/research/chousa/pdf/r4/2022honshi_all.pdf
小さな子どもがいる人
大学卒業までにかかる平均的な教育費(下宿費・住宅費は除く)は、全て国公立でも1,000万円を超え、全て私立だと約2,600万円以上に上る、と言われています。
小さなお子様がいる家庭では、教育以外のお金も含めると、子育てにかかる将来的な支出はかなり大きな負担になります。
主要な収入源である親が病気やケガにより、長期間働けなくなると、教育資金の確保が難しくなる可能性があります。
結果、お子様に満足のいく教育を受けさせることができなくなるかもしれません。
医療保険に加入することで、長期の入院時の収入の減少をカバーすることができます。
小さなお子様がいる家庭では、医療保険の加入を検討されても良いかもしれません。
参照:文部科学省「令和5年子供の学習費調査」
https://www.mext.go.jp/content/20241225-mxt_chousa01_000039333_1.pdf
参照:日本政策金融公庫~令和3年度「教育費負担の実態調査結果」~
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/kyouikuhi_chousa_k_r03.pdf
まとめ
何より大切なのは、その時にご自身が支払いや生活に困らないようにしておくということです。
そのためには、入院した時に何のための資金がいくら必要かを概算でも把握しておくことが大切です。それがどのくらいか分かりにくい場合は、我々FPに気軽に相談して頂ければと思います。
執筆者:ほけんペディア編集部