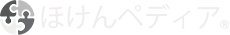「お宝保険」って聞かれたことありますか。保険という名前が付いていますが、決して商品名ではありません。
一般的には、貯蓄性が高くバブル崩壊前の景気が良かった時、つまり保険の予定利率が高い時に契約した保険を指します。
もしご自身が加入している保険がお宝保険だった場合、保険の見直しをすると大変勿体ないことになるかもしれません。
今回は、「お宝保険」の特徴や、解約する前に確認しておきたいポイントを解説します。保険の解約や見直しをする前にぜひご加入の保険がお宝保険かどうか確認しましょう。
今では絶対入れない『お宝保険』とは?
まず、お宝保険についての説明をします。一般的にはバブル崩壊前の景気が良く保険の予定利率が高かった時に契約した保険で、貯蓄性が高い保険のことを言います。
保険商品は、原則としてご加入時の予定利率が保険終了時まで変わらず継続するようになっています。
そのため、昨今の超低金利時代においてもバブル時の高金利で運用されています。
加えて予定利率が高いと保険料が安くなるため、同じ条件の保険契約を今の保険と比較すると保険料が非常に安い、しかもお金も増える、でも今からは決して加入できない。まさに「お宝」のような保険なのです。
昔入った保険がお宝保険に
お宝保険に該当する保険は、いつ頃契約したどのような保険種類のものを指すのでしょうか。
具体的な保険種類については、終身保険(一生涯保障のある保険)、養老保険(満期のある保険)、年金保険になります。
若い時にとりあえず加入したまま放置していたとか、親御さんが加入してくれていたといった事例をよく聞きます。
読者のなかにも、実は若い時にお宝保険に加入していたということも考えられますので今一度ご自身が契約されている保険を確認してみましょう。
予定利率とは
予定利率とは、生命保険会社がご契約者に約束する運用利回りのことです。予定利率は、金融庁の定めた標準利率に基づいて計算されます。
この予定利率は、いつ保険にご加入されたかで変わりますので高い予定利率で加入したかどうかがお宝保険かどうかのポイントになります。では、生命保険の予定利率の変遷をみていきましょう。
| 期間 | 予定利率 |
|---|---|
| ①1985.4~90.3 | 保険期間が20年超のものは5.5%です。 |
| ②1990.4~93.3 | 保険期間が10年超5.5% |
| ③1993.4~94.3 | 4.75% |
| ④1994.4~96.3 | 3.75% |
| ⑤1996.4~99.3 | 2.75% |
| ⑥1999.4~2001.3 | 2% |
| ⑦2001.4~2013.3 | 1.5% |
| ⑧2013.4~2017.3 | 1% |
| ⑨2017.4~ | 0.25% |
となっています。
今は、なんと0.25%で、今までで最低の予定利率になってしまっているのです。
一般的には、④96年3月までの予定利率が3.75%のものを「お宝保険」と言います。払い込んだ保険料より増えるのが当たり前で、保険期間にもよりますが、中には2倍近く増えるものもあった時の商品になります。
お宝保険の見分け方
お手元に保険証券を用意して、契約日がいつか、商品名(終身・養老・年金保険)が何かをしっかり確認しましょう。または保険会社から定期的に送られてくるご契約内容のお知らせなどにも記載があります。中には、予定利率が記載されているものもあります。上述の通り、貯蓄性が高い保険商品で、なおかつ予定利率が3.75%以上の場合、「お宝保険」と判断して良いでしょう。
お宝保険の解約には慎重になるべき3つの理由
今からでは決して加入できないお宝保険ですから、見直し・解約には是非とも慎重になっていただきたいです。
ここでは見直しを慎重に行なって欲しい理由を説明させて頂きます。
保険料が安いのに、受け取れるお金が多いから
予定利率が高いため保険料は安くなります。解約返戻金が同じだとしても保険料が安くなるため、運用利回りが高くなり、結果貯蓄性も高くなります。
現時点で同様の保険内容で加入する場合で比較すると、特に解約返戻率においてはその差は歴然です。
ローリスク・ハイリターンだから
ご存知の通り、現在の大手都市銀行の1000万円以上の大口定期預金金利が0.002%(2021年12月現在)という超低金利時代です。
保険と他の金融商品と単純には比較できませんが、保障もついて予定利率が3%以上の保険商品に匹敵する金融商品は、今のご時世にはほとんどありません。現在の金融商品でお宝保険と同じリターンを得ることは非常に困難だと言えます。
一度解約すると入り直せないから
お宝保険か否かは、加入時の予定利率で決まります。保険商品は、原則としてご加入時の予定利率が保険終了時まで継続するようになっているからです。
従って、解約をして入り直すと現在の低い予定利率での加入になります。それに加えて年齢や健康状態、払込期間などの関係もありますので同じ条件では加入ができません。
お宝保険を最大限活かす受け取り方
ではご加入の保険がお宝保険だった場合、どのように保険金を受け取るのが良いのでしょうか。
ここではお宝保険の中でも代表的な年金保険について、その受け取り方法・気をつけて頂きたいことを説明します。
年金保険は、保険料の払い込みが終了し年金の受け取りが開始された時には、一括受け取りと年金形式での受け取りの2種類の方法があります。(契約者と受取人が同一であるとしてお話させて頂きます。)
一括受け取りは、年金形式の分割でもらうのではなく一回でまとまった金額を受け取る方法になります。まとまった金額を1回で受け取ることが大きなメリットになりますが、その一方で年金形式での受取総額と比較して目減りしてしまうため、受取額が少なくなることがデメリットになります。
また一括受け取りの場合は、受け取った金額は一時所得になり、年金形式受け取りの場合の雑所得とは異なる課税になります。
一時所得の場合の課税所得金額は、
{総収入額(年金一括受取額)- 必要経費(総支払保険料)- 50万円}× 50% = 一時所得の課税所得金額
となり総支払保険料より受取額が50万円以上増えてなければ税金はかかりません。
一方の年金形式受け取りは、決められた期間、あるいは終身までずっと一定の金額を分割して受け取る方法になります。
この場合の課税額の計算方法は以下の通りです。
収入(年金受取額)- 必要経費 = 雑所得 になります。
必要経費 = 年金受取額 ×(総支払保険料 ÷ 年金受取総額)
お宝保険の年金保険の場合、一括受け取りのほうが税金面で負担が少なくなることがあるので、注意が必要です。
お宝保険の中途解約前に検討したい3つの選択肢
お宝保険に加入しているため解約は避けたいが、家計が苦しいというケースも十分に考えられるでしょう。ここで知っていただきたいのは、解約以外にも月々の保険料負担を軽減することができるという点についてです。
ここでは、お宝保険の解約前に検討すべき3つの方法をお伝えします。
自動貸付制度
一時的に保険料の都合がつかないときに契約の失効を防ぐため、保険会社が解約返戻金の決められた範囲内で保険料を自動的に貸し付け、契約を有効に継続させる方法です。ただ貸し付けられた保険料には所定の利息が付きます。貸付金は、全額または一部をいつでも返済することができます。
なお、お宝保険の場合は予定利率が高いため、それに応じて貸付金利も高くなる点については、注意が必要です。
払済保険
払済保険とは、読んで字のごとく加入の保険の保障期間を変えずに保険料の支払いを済ませるということです。
保障額をその時点での解約返戻金の原資にみあった金額に下げて保険を継続する方法です。変更することでその時点から保険料が発生せず以後の保険料負担を無くすことが可能です。勿論払い済み後もお宝保険の高い予定利率での運用は継続されます。ただ基本的には、一度払済保険へと変更してしまった場合元には戻せません。
契約者貸付制度
貯まっている解約返戻金を担保に保険会社からお金を借りる方法です。借り入れできる範囲は保険会社ごとに異なり、また同じ保険会社でも保険商品ごとに異なることがありますが、解約返戻金の70%~90%の範囲の場合が一般的です。返済については、借入金の利息分だけの返済、借入金の一部分だけの返済、借入金全額の返済など契約者の資金計画に応じて自由に返済することができます。ただ、自動貸付制度と同様に予定利率が高い分、金利が高くなる点は注意が必要です。
まとめ
今回は、「お宝保険」の特徴や、解約する前に確認しておきたいポイントを解説してきました。現代の超低金利時代においては想像もできないような好条件で保険加入できている場合、その恩恵を最大限享受したいものです。
お宝保険は、今から加入できない非常に良いものです。見直しする際には、よく保障内容を理解し安易に解約することなくしっかり検討しましょう。ご自身で判断できない時には、保険に詳しいファイナンシャルプランナーに相談しましょう。