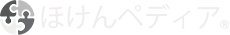車を運転していると『ドキッ!』とすることありませんか?
いくら自分で注意していても突発的な事なので避けられない事故もありますよね。
そんな事故が起きた際に被害者や加害者の経済的な補償をしてくれるのが自動車保険です。
では、生命保険も「もしものときのために」加入しているという観点では同じですが、交通事故の場合は保険金や給付金の支払対象となるのでしょうか?
交通事故の場合「自動車保険からは支払われるけど、生命保険や医療保険から保険金や給付金は支払われないのでは?」と思われる方も多いのではないでしょうか。
ここでは交通事故における生命保険の役割と保険証券や設計書を見てもなかなかわかりにくい保障の範囲や特約について説明します。
交通事故の際に生命保険は適用される
生命保険はその名のとおり生命(人)を対象とした保険ですので被保険者(個人)が死亡した場合に死亡保険金が支払われる商品となります。
死亡保険金の支払いは、病気が原因でも交通事故が原因でも死亡保険金支払いの適用となります。
生命保険の適用範囲
交通事故で亡くなってしまった場合に生命保険は支払いの適用となりますが、それでは交通事故など不慮の事故でケガをしてしまった場合はどうでしょう?(※不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故のことを言います。)
生命保険は、死亡保障の他に病気やケガで入院・手術をした際にも【給付金】という形での支払い対象となります。
これらは主に、医療保険や死亡保障契約の特約で保障されています。
- 病気に対する保障
被保険者が病気により入院をした場合や手術を受けた場合に、入院険給付金や手術給付金が支払われます。
- 交通事故やケガに対する保障
交通事故やケガなど不慮の事故により入院した場合や身体障害になってしまった場合に、入院給付金・手術給付金や保険金が支払われます。
交通事故の際に適用される保障
生命保険は被保険者が死亡や入院・手術をされた際に保障されるものです。被保険者が交通事故に遭い何らかのケガを負ってしまった場合、考えられるケースとして2つあります。
①死亡してしまうケースと②ケガで入院・手術となるケースです。
①死亡してしまうケースでは、【死亡保険金】の支払い対象となります。
例えば、死亡保険金3000万円で契約していた場合は3000万円が保険金受取人に支払われます。
②ケガで入院・手術となるケースでは、医療保障の【入院・手術給付金】の支払い対象となります。
契約している入院日額や手術給付金、入院一時金等が被保険者に支払われます。
生命保険と損害保険の違い
交通事故に備える保険として、生命保険と損害保険があることはご存知の通りです。
両者を比べてみると、生命保険はケガに加えて病気でも保障を受けられますが、損害保険は一般的にケガのみの保障となります。
それぞれの特徴を確認しましょう。
生命保険の特徴
生命保険の中でも医療保険は、交通事故などの不慮の事故だけでなく病気による治療も保障しています。
また特約の付加により自身に必要な保障を厚くすることができます。
保険期間や払込期間の選択肢も多く比較的自由に商品設計できますし、生命保険は契約した金額が定額で支払われるというのも大きな特徴です。
損害保険の特徴
損害保険の傷害保険は、交通事故などの不慮の事故やケガの場合のみ保障しているため保険料が比較的安価という特徴があります。
死亡、後遺症、入院、手術、通院、ケガをさせてしまった場合の賠償など主に事故によるケガの保障について広くカバーしています。また損害保険の保険金は、基本的に実費での支払いとなる点が生命保険と大きく異なる点です。
※2001年7月より生命保険会社と損害保険会社の両社で医療保険や傷害保険を販売できるようになりました。
どちらも交通事故への備えで加入すべき
一般的に交通事故への備えとして、生命保険と損害保険の両方に加入しておくのが望ましいでしょう。
両者は支払事由や受け取る保障(補償)金額、そして保障(補償)範囲が異なっており、互いにカバーし合う関係だからです。
上述したように生命保険と損害保険では保険金等の支払われ方が異なります。事故に遭った時を想定して必要な保障を揃えましょう。
また、生命保険では被保険者が交通事故の場合に支払い対象となりますが、その一方でその際に同乗していた人や相手に対する保障は準備できません。
交通事故に備えるための生命保険特約4選
生命保険では、被保険者が交通事故により死亡、あるいはケガをしてしまった場合、主契約による保障に加えて、加入している特約によって主契約の保険金額より上乗せした金額を受け取れることができます。
特約とはオプションのことで主契約に付加する保障となります。
たとえば、主契約が3000万円の死亡保障で、ここに特約で1000万円の災害割増特約を付加した場合を考えてみます。
この場合、被保険者がもし交通事故で亡くなった場合には合計4000万円の死亡保険金が支払われます。
それでは交通事故に関連する特約を見てみましょう。
災害入院特約
不慮の事故による傷害の治療を目的として入院した場合に支払われる給付金のことで入院日数に応じた入院給付金や手術給付金が支払われます。
災害割増特約
不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日も含めて180日以内に死亡した場合や高度障害状態に該当した場合に、主契約の死亡保険金に上乗せして支払われる保険金です。
また、約款に定める感染症による原因の場合も支払われます。
傷害特約
不慮の事故により死亡した場合や高度障害状態に該当した場合に死亡保険金に上乗せして給付される点では災害割増特約と同じですが、所定の身体障害状態に該当した場合には等級に応じて傷害保険金が支払われるなど、災害割増特約よりも保障が厚くなるのが特徴です。
不慮の事故から180日以内に死亡した場合や感染症などで死亡した場合に死亡保険金に上乗せして支払われます。
特定損傷特約
不慮の事故の日から180日以内に「骨折、間接脱臼、腱の断裂など」に対する治療が行われた場合に、保険給付金が支払われます。
スポーツ中の事故も対象としている保険会社も多く、骨が折れたり、ひびが入ったり入院や手術をしないケースでも給付されるのが特徴です。
交通事故時の生命保険の請求方法3ステップ
ここでは交通事故に遭ってしまった後に生命保険を請求する方法について3ステップに分けて解説していきます。
生命保険会社に連絡をする
交通事故によって被保険者の死亡・入院・手術など保険金・給付金の支払い事由が発生した場合には、すみやかに、ご加入された保険会社、または契約の手続きをされた代理店に連絡しましょう。
また、保険金・給付金は受取人本人の請求によって支払われるものなので、受取人本人から連絡しましょう。
(※「指定代理請求人」が指定されている場合には、代理人が請求できる場合もあります。)
その際に、保険証券番号がわかると手続きがスムーズに進みますのでもし手元に準備できる余裕がある場合には保険証券番号を用意しておきましょう。
また、交通事故による請求の場合には事故発生状況報告書(※1)や交通事故証明書(※2)が必要となりますので、生命保険会社に連絡をするタイミングで早めに請求するほうが良いでしょう。
(※1) 事故発生状況報告書: 保険会社に保険金を請求する際に必要な交通事故の発生状況を説明するための書類。保険金請求者が記入。
(※2) 交通事故証明書: 事故が起きたという事実を証明する書類。警察に届出を行ったあとに申請すると、各都道府県の自動車安全運転センターが発行。
医師から診断書をもらう
生命保険会社への請求の際には、入院期間や手術の内容など記載した診断書を医師から取得し提出することになります。
この診断書は生命保険会社ごとに書式が異なっております。他社の診断書のコピーでも大丈夫という保険会社もありますが、複数の保険に加入されている場合には注意が必要です。
また、診断書の取得には診断書代として費用がかかります。
診断書についてはこちらの記事も参考にしてください。
 医療保険を有効にきっちりと活用するために必要な診断書の受け取り方や、その際にかかる費用、受け取り時の注意点さらには給付金等の請求の仕方について解説しています。
医療保険を有効にきっちりと活用するために必要な診断書の受け取り方や、その際にかかる費用、受け取り時の注意点さらには給付金等の請求の仕方について解説しています。
必要書類を揃えて返送する
請求に必要な書類は下記の通りです。保険会社や請求の内容によって必要書類も異なります。不明な点は保険会社や担当者に確認しましょう。
主な必要書類
死亡の場合
- 証券番号
- 死亡保険金請求書
- 保険金受取人の戸籍謄本
- 保険金受取人の印鑑証明書
- 被保険者の住民票
- 死亡診断書(死体検案書)
- 事故発生状況報告書(テンプレートは保険会社に依頼)
入院・手術・通院の場合
- 給付金請求書
- 入院・手術等診断書(証明書)
※保険会社所定のもの - 事故発生状況報告書(テンプレートは保険会社に依頼)
交通事故時の生命保険に関わるQ&A
交通事故によるむちうちでの通院で生命保険は適用されますか?
交通事故で追突されたりすると、「むちうち」になるケースがあります。
むちうちの具体的な症状としては首筋や背中、肩あたりの痛みまたは凝りなどです。そのほかには頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気などを生じることもあります。
これからの症状が出て「むちうち」となった場合に生命保険の支払い対象となるのでしょうか。
むちうちは一般的には自動車保険の対人保険では補償の対象となることが多いようですが、治療が主に通院のみとなることから、生命保険の場合はむちうちの症状で給付金等が支払われる例はあまり多くありません。
入院せずに通院治療だけでは生命保険の通院特約では適用の範囲外となります。
入院をしていない通院の場合は出ないケースが多いのです。
交通事故に備えるために生命保険の特約に入る必要はありますか?
「交通事故に備えるため」となるとやはり損害保険での自動車保険や傷害保険を充実させるほうが良いでしょう。
生命保険では保障(補償)されない賠償責任の補償が損害保険にはあります。
ただ、損害保険では実費払いとなります。基本的には交通事故による経済的損失の補填という要素が強いため、実費以上の補償を金銭面でカバーするには生命保険の備えがあると安心と言えます。
前述しましたように、生命保険は死亡や病気、ケガなどあらゆるケースにて支払い対象となります。
生命保険に加入していれば交通事故の際にケガの治療の保障は得られますので「生命保険に加入しているので交通事故の際のケガの治療に関する保障はカバーされている」という認識で良いでしょう。
また特約に関しては、必ず付加しなければならないというものではなく、保障のニーズがある場合に備えればよいと思います。
まとめ
交通事故の際の保障としての生命保険の解説をさせていただきましたが、いかがでしたか?
交通事故による保障(補償)だけでみると損害保険会社の傷害保険でカバーできることが多いですが、生命保険で準備する場合は病気や介護などの保障も同時に備えることができます。
傷害保険は今では保険会社だけでなくクレジットカード会社や共済、団体など取り扱いしている代理店が数多くあります。
また、保険期間が1年更新であり、保険料も比較的安価であるため知らないうちに他の保険と補償が被ってしまうこともあります。
これらを踏まえてご自身やご家族がどのようなときにいくら保険金や給付金が支払われるのか、その保険金や給付金により経済的な負担をどれだけカバーできるのか確認する時間を一度設けてみてはいかがでしょうか?
また、今回解説させていただきました内容については保険会社や商品によっては支払事由が異なりますので不明な場合は保険のプロであるFPに相談すると良いでしょう。